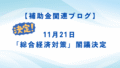つまみ食い的外部活用のすすめ

現在、葬祭業は、2040年頃まで続く葬儀需要のピークと、それに伴う競争の激化、そして業界全体の宿命である人手不足という複合的な課題に直面しています。
こうした厳しい環境下で、いかに少ないリソースで、競争力を高めていくかが問われています。本稿では、人手不足時代を乗り切るための「生き残りの鍵」の一つとして、従来の自前主義から脱却し、「つまみ食い的外部活用」を戦略的に進める方法について解説いたします。
目次
1. 業界の宿命:人手不足と「すべて自前主義」の限界
人手不足は、今後もこの葬祭業界にずっと続く宿命であると認識しなければなりません。人が減り採用が困難な中で、今いる人材でいかに業務を効率よく回すか、すなわち生産性の向上が求められています。
この状況下で、従来の「すべてを自社でやる」という自前主義は、限界を迎えています。例えば、デジタルマーケティングの専門知識、高度な人事評価制度の構築、補助金申請サポートなど、専門性の高い分野が多岐にわたる現代において、これら全てに対応できる専門人材を社内で育成しようとすると、「すごいレベルが高いし、費用もかかっちゃう」という高いハードルが生じます。
この非効率を回避し、自社のリソースを主業務(お客様対応や施行)に集中させるためにも、外部の力を賢く利用する戦略が必要不可欠となります。
2. 生き残りの鍵:「つまみ食い的外部連携」のすすめ
これからの生き残りの鍵の一つとして挙げられているのが、「外部連携の強化」です。これはマーケティングなど主業務以外の外注化を指しますが、重要なのはその連携の仕方です。
本稿で提唱するのは、「つまみ食い」の考え方です。
これは、外部の会社を長期的に囲い込むのではなく、自社の課題解決や競争力強化のために、必要な専門知識や技術を必要な期間だけ、スポットで利用するという戦略です。
外部には、マーケティングや人事のプロフェッショナルな会社が多数存在します。彼らは常に市場の変化に合わせて差別化を図っており、最新の知識やノウハウを持っています。自社で高い費用と時間をかけて育成する代わりに、外部の主要な会社さんを「自社のように使う」という発想の転換が、コスト削減と競争力の向上につながります。
3. 外部連携を強化すべき具体的な業務領域とメリット
外部連携を強化すべき業務領域は、主に主業務以外の、高い専門性を要する分野です。
具体的な連携の例:
- マーケティング分野: ウェブ広告やSEO、SNS戦略など、トレンドの移り変わりが激しい分野。**「マーケティングの旬のところだったら、マーケティングで旬の会社と一旦付き合ってみて、また時期が来たら違う会社を試してみる」**といった柔軟な活用が可能です。
- 人事・採用分野: 高度な賃金体系や評価制度の設計、外国人労働者の受け入れ体制構築など。
- 補助金・法務分野: 国の省力化投資促進プランやIT導入補助金の活用、複雑な死後事務委任契約など、専門資格を要する業務。
外部連携のメリットは、自社の社員を高度な専門知識のインプットや研修に割く必要がなくなるため、人材育成コストが削減できる点に尽きます。結果として、浮いたリソースを、収益に直結するお客様対応や施行品質の向上に集中させることができます。
4. 外部活用とDX/AI活用の戦略的な住み分け
人手不足対策は、「生産性の向上(DX/AI活用)」と「外部連携の強化」という二本柱で進める必要があります。ここで重要なのが、この二つの戦略の住み分けです。
AIの急速な発展により、外注をせずに内製化を進めたほうが望ましい分野も増えてきました。このため、コンテンツ制作や定型化できる業務や大量の情報処理が必要な業務は、自社でAIを導入し、省力化すべきです。
一方、外部連携は、AIでは代替できない高度な戦略構築や、専門家によるマンパワーやノウハウが必要な分野(例:旬のマーケティング会社の持つ非公開ノウハウ、専門家による伴走型コンサルティングなど)に特化して行うべきであり、この戦略的な役割分担が、現代の競争環境を勝ち抜く鍵となります。
5. 終わりに:新公式にみる外部連携の役割
「つまみ食い的外部活用」は、人手不足という業界の宿命に対応し、AIとのすみ分けを適宜図りつつ、生産性を向上するための現実的かつ戦略的なアプローチです。外部のプロフェッショナルを賢くスポット活用し、自社のコアコンピタンスである「人の力」を、お客様への真摯な対応と施行品質の向上に集中させましょう。