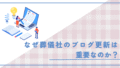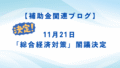葬儀代トラブルが過去最多に|相談978件から見る注意点と対策
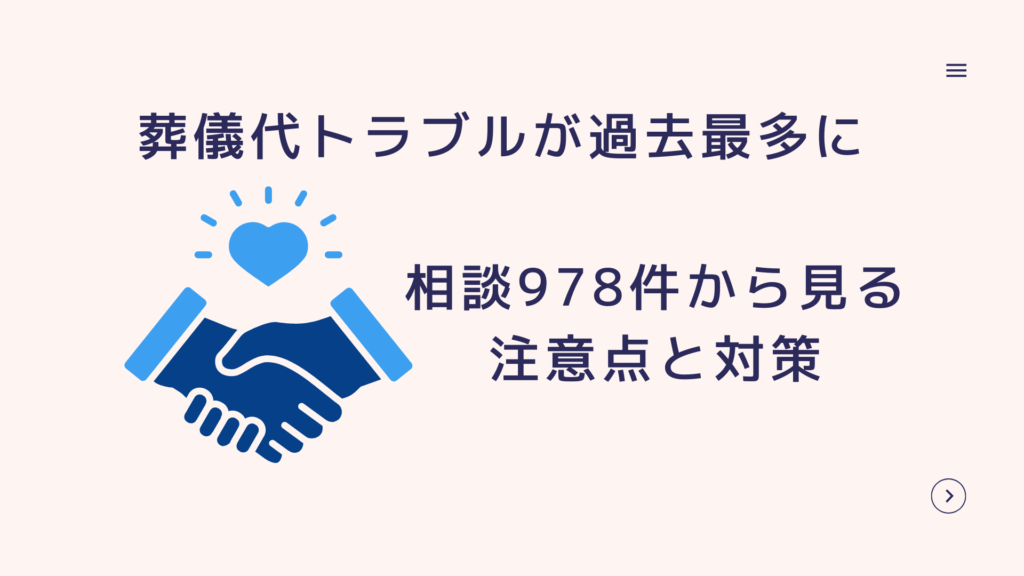
「思った以上に高額な請求をされた…」
「見積もりにない費用が後から加算された…」
近年、葬儀費用に関する消費者トラブルが増え続けています。
国民生活センターに寄せられた「葬儀サービス」に関する相談件数は 2024年度に978件(過去最多)。
終活が広まる一方で、費用や契約面の“情報格差”が浮き彫りになっている状況です。
本記事では、公開データをもとにトラブル増加の背景と、葬儀社が取り組むべき対策をまとめます。
目次
■ 消費者相談件数が過去最多に達した背景
国民生活センターの統計では、葬儀サービスの相談件数は以下のとおり推移しています。
| 年度 | 相談件数(葬儀サービス) |
|---|---|
| 2022年度 | 951件 |
| 2023年度 | 886件 |
| 2024年度 | 978件(最多) |
件数が増えている背景には、次の要因が考えられます。
|家族葬・直葬の広がりと“価格の不透明さ”
シンプルなプランを謳いながら、
「HP掲載の金額と請求額が違う」
といった相談が増加しています。
|ネット経由の申し込み増加
ポータルサイト・ネット葬儀社での契約は便利ですが、
説明不足のまま申し込みまで進んでしまうことも。
|業界の新規参入と品質のバラつき
新規参入が増え、経験やガイドライン理解の不十分さが原因となるケースもあります。
■ よくある葬儀代トラブルのパターン
相談内容は多岐にわたりますが、代表的な例は以下の通りです。
見積書と最終請求額の乖離
|事前説明のない追加費用が積み上がり、
「想定の2〜3倍になった」という相談も。
|“一式表示”で内訳が不明確
「葬儀一式◯◯万円」と記載されていても、
実際には多数のオプションが後から加算されることがあります。
|契約内容と異なるサービスの提供
例:通夜なしプランを選んだのに、通夜費用が組み込まれている など。
■ 全葬連の「葬祭サービスガイドライン」とは?
全日本葬祭業協同組合連合会(全葬連)は、業界の透明性向上のために「葬祭サービスガイドライン」を制定しています。
主なポイントは次の通りです。
- 内訳を明示した見積書の書面交付
- 「一式」「パック」表示には構成要素を明記
- 消費税の表示方法(内税・外税)の明示
- 追加・変更時の説明と遺族代表者の確認
- 葬儀後の請求書交付と明細提示
特に見積書に関しては、あいまいな表現を避け、
“誰が見ても理解できる内容”が求められています。
■ トラブルを未然に防ぐためのチェックポイント
葬儀社として信頼を得るためには、透明性を軸にした体制が不可欠です。
以下の観点を今一度チェックしてみてください。
✅ 1|わかりやすい見積書の作成
- 全項目を明細形式で記載
- 「必須」「任意」「オプション」を明確化
- 説明内容を備忘録として残す
✅ 2|HP掲載価格との乖離をなくす
- 含まれない項目は注記として明記
- 「最小費用」「平均実費」の2段構成で提示すると誤解が減る
✅ 3|担当者スキルと説明の統一
- 提案内容が担当者ごとに違うと不信感につながる
- 営業マニュアル・説明資料を統一して、質を均一化
■ これから求められるのは“透明性”と“誠実さ”
高齢化、単身世帯増加、比較サイト文化の浸透――
消費者の意思決定はますます複雑になっています。
今の時代、選ばれる葬儀社の条件はシンプルです。
「透明性」
「誠実な説明」
「納得できる価格提示」
「安いから」「見つけやすいから」だけで選ばれる時代は終わりに近づいています。
情報を正しく開示できる葬儀社こそ、長く選ばれていくでしょう。
■ まとめ
- 2024年度の葬儀サービス相談件数は978件(過去最多)
- 主なトラブルは「見積との差」「一式表示」「意図しないサービス提供」
- 全葬連のガイドラインで“内訳明示・説明義務”が明確化
- 信頼される葬儀社には、見積書・説明・HP掲載内容の透明性が不可欠
最後にひと言。
「わかりやすい、誠実な説明を。」
これが、これからの葬儀社経営における最大の差別化ポイントになるはずです。