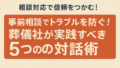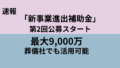11月は“終活の好機”!地域に信頼を育む「終活相談会」成功の5ステップ
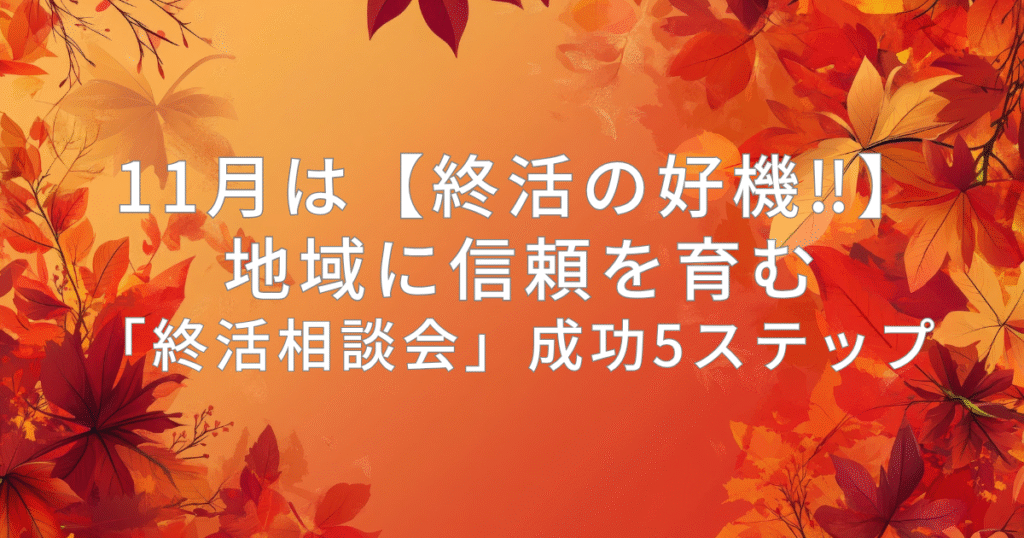
秋が深まり、街路樹が色づく11月。
お彼岸が過ぎ、年末が近づくこの時期は、「そろそろ終活を考えようかな」と意識する方が増える季節です。
親族と顔を合わせる機会も多く、「お墓や相続、どうしておこうか」という話題が自然と出やすいタイミングでもあります。
葬儀社にとっては、“地域の方々と信頼関係を築く絶好のチャンス”。
一方で、
「終活相談会を開いても人が集まらない」
「続けたいけれど、ネタが続かない」
と悩む声も多く聞かれます。
今回は、11月からの開催にもぴったりな
“地域で信頼を得ながら成果を生む終活相談会”の開き方を、5つのステップでご紹介します。
目次
① 売り込みではなく、“寄り添い”の姿勢を徹底する
終活相談会を成功させる第一歩は、「販売イベント」ではなく“対話の場”として捉えること。
参加者が求めているのは、商品やサービスよりも「話を聞いてもらえる安心感」です。
「押し売りされそう」という印象を避けるためにも、
やさしく温かい表現で案内しましょう。
例:
- 人生の整理を一緒に考える「終活カフェ」
- 気軽に立ち寄れる「地域の終活サロン」
- 供養・相続・お墓・葬儀の「なんでも安心相談会」
11月は寒さが増し、人恋しさや不安を感じやすい季節。
“寄り添う言葉”が、参加へのハードルを下げてくれます。
② ターゲットを明確にして、テーマを絞る
「終活」といっても、関心のあるテーマは人によって違います。
成果を出すには「誰の悩みを解決する相談会なのか」を明確にすることが大切です。
| 世代 | 主な関心テーマ |
|---|---|
| 50代 | 親の介護・相続・実家の整理 |
| 60代 | 自分の葬儀やお墓の準備 |
| 70代以上 | 身近な人の経験を通じた“自分ごと”としての終活 |
「親のための終活セミナー」や「年内に考える自分らしいお葬式」など、
テーマを具体的にすると集客効果が高まります。
③ 専門家と連携して“信頼性”を高める
単独開催よりも、他業種とコラボした方が効果的です。
特に相続・遺言・保険・お墓・介護などの分野と組むと、参加者の興味が広がります。
連携例:
- 司法書士や行政書士との「相続と供養セミナー」
- 仏壇店との「お墓とお仏壇の整理相談会」
- 保険会社との「もしもの時の備え講座」
地域の専門家と一緒に行うことで、「安心して相談できる葬儀社」という信頼が生まれます。
④ SNS・チラシ・口コミで効果的に告知する
11月は行事やイベントが多く、地域の方々が動きやすい時期。
2〜3週間前からの告知が理想です。
おすすめの告知方法:
- Instagram・Facebook: 写真+地域名で投稿(例:「〇〇市で終活相談会を開催します!」)
- 地域掲示板・回覧板: 高齢層に確実に届く
- 寺院・介護施設・病院: チラシ設置で新しい層にリーチ
- 既存顧客へのDM・ニュースレター: 信頼関係のある方からの紹介につながる
「参加無料」「予約制」「少人数制」といったキーワードを添えることで、
安心して参加できる印象を与えます。
⑤ “次につながる仕組み”を意識する
一度の相談会で終わらせず、継続的な関係づくりを意識しましょう。
フォローの工夫:
- 「供養ガイドブック」や「終活ノート」を参加特典に
- 季節のお便りや年末の感謝ハガキを送付
- 参加者限定の「家族葬セミナー」や「ホール見学会」へ招待
「一度来て終わり」ではなく、「また話を聞きたい」と思ってもらえる関係を目指しましょう。
まとめ:年内最後の信頼づくりチャンス
11月は、“終活を考え始める人”と“今年中に準備を済ませたい人”が重なる時期です。
このタイミングでの終活相談会は、地域に寄り添う姿勢を発信できる絶好の機会です。
成功の5ポイント:
- 売り込みではなく寄り添いの姿勢
- ターゲットとテーマを明確に
- 専門家との連携で信頼性アップ
- SNS・チラシ・口コミで広報強化
- イベント後のフォローで関係継続
「終活相談会」を通じて、“地域に愛される葬儀社”としての存在感を高めていきましょう。