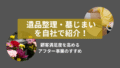【葬祭業向け助成金】葬儀社も対象!厚生労働省の助成金で現場改革を!
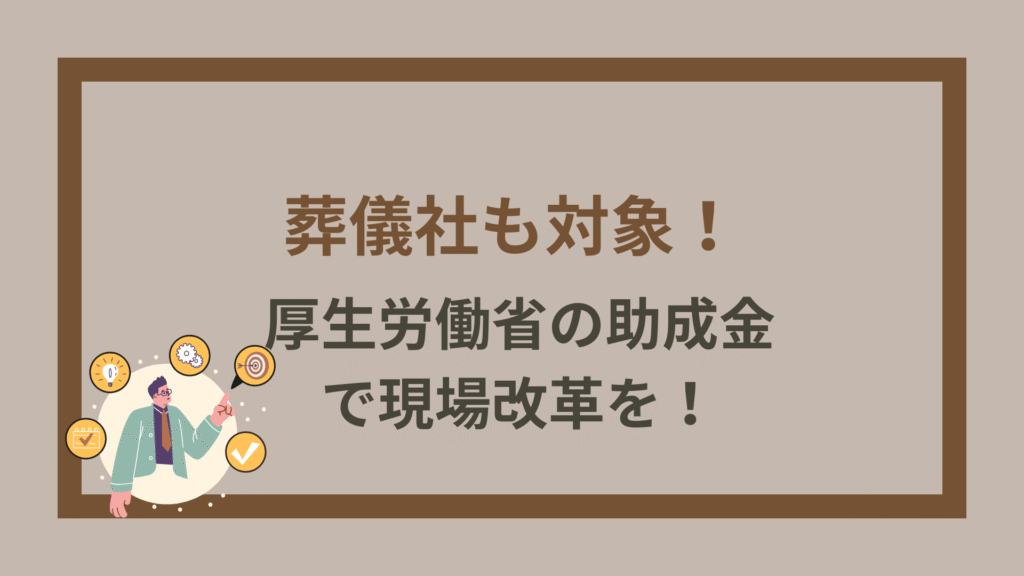
【葬儀社も対象】厚生労働省の助成金で現場改革を!
――人材定着・研修・設備投資にも使える支援制度とは
目次
はじめに:補助金だけで満足していませんか?
「補助金は申請しているけれど、助成金までは調べていない」
そんな葬儀社様も少なくありません。
しかし、実は葬儀社も厚生労働省の助成金の対象になることをご存じでしょうか?
助成金は、返済不要なうえに条件を満たせば原則もらえる制度。
さらに、人材の定着・教育・働きやすい職場づくりなど、現場課題の解決に直結します。
本記事では、葬儀社が活用できる代表的な助成金と、その活用ポイントをご紹介します。
葬儀社も対象!助成金の基本
厚生労働省の助成金は、雇用保険に加入している事業者であれば原則対象となります。
つまり、従業員を1人でも雇用している葬儀社は申請可能です。
助成金は「働く人を守りながら、企業の生産性を高める」ことを目的にしており、
人手不足・離職率の高さ・教育コストなどに悩む葬祭業とは非常に相性が良い制度です。
葬儀社が活用しやすい助成金4選
① キャリアアップ助成金(非正規→正社員転換など)
- 対象例:パート・アルバイト・夜間待機スタッフなどを正社員登用
- 支給額:1人あたり最大80万円
- 活用例:
・式場スタッフを正社員化し、夜間・休日対応を安定確保
・登用制度の整備により、離職率が大幅に減少
💡 ポイント
助成金は「事前申請」が必須。転換前に計画を出しておく必要があります。
② 人材開発支援助成金(研修・教育訓練)
- 対象例:新人研修/司会・納棺・搬送スタッフのスキルアップ研修など
- 支給額:研修費+賃金助成(1人1時間あたり約760〜960円)
- 活用例:
・葬祭ディレクター研修を実施し、葬儀全体の品質を統一
・接遇研修や電話対応研修で顧客満足度が向上
💡 「人を育てる会社」は採用にも強くなる!
教育投資を助成金で賢く補うことができます。
③ 業務改善助成金(設備投資・職場環境改善)
- 対象例:
・会館設備や空調・照明の改善
・搬送車・ストレッチャー・管理システムなど業務効率化設備の導入 - 支給額:最大600万円
- 活用例:
・業務管理システムを導入して事務負担を軽減
・職員の残業時間削減と労働生産性アップを実現
💡 「設備投資×働きやすさ」で現場改革に直結する人気制度です。
④ 両立支援等助成金(働き方改革・育児介護支援)
- 対象例:
・育児・介護と両立しながら働けるシフト体制の整備
・短時間勤務や在宅業務の導入 - 支給額:1人あたり最大57万円〜
- 活用例:
・女性司会スタッフの育休復職支援で、優秀人材の定着につながった
・柔軟な勤務制度が採用PRにも効果を発揮
💡 「働き方の柔軟性」は今後の採用競争においても大きな差別化ポイントです。
助成金を活用する際の注意点
助成金は魅力的な制度ですが、申請には正しい手続きと事前計画が必要です。
注意すべきポイントは以下の通りです。
- 対象制度によって必要書類や申請期間が異なる
- 事前に計画書提出が必要なケースが多い
- 雇用契約書・賃金台帳・研修記録など証拠書類の保存が必須
- 手続きは**社会保険労務士(社労士)**の専門分野
どの助成金に該当するか分からない場合は、社労士や専門機関の無料相談を利用するのがおすすめです。
助成金で「人を育てる会社」へ
補助金は新しいサービスや設備投資に活用されることが多いですが、
助成金は**“人”に投資する制度**です。
- 人材が定着する
- 教育レベルが上がる
- 現場の生産性が向上する
- 離職率が下がる
こうした効果は、葬儀社の信頼や顧客満足にも直結します。
まさに「人を大切にする企業」に向けた支援策といえるでしょう。
まとめ:補助金+助成金で経営を強くする
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 葬儀社・葬祭ホール・関連事業すべて |
| 条件 | 雇用保険加入の従業員がいること |
| 主な助成金 | キャリアアップ/人材開発支援/業務改善/両立支援など |
| 管轄 | 厚生労働省(ハローワーク・労働局) |
| タイミング | 毎年募集、随時申請可能 |
「補助金で設備を」「助成金で人を」
両輪で活用することで、葬儀社経営の基盤はより強くなります。
来年度の募集開始前に、ぜひ自社で使える助成金をチェックしてみてください。
人材に投資することが、未来のお客様への信頼につながります。