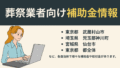地域包括支援センターと連携して進める「終身サポート事業」の広げ方
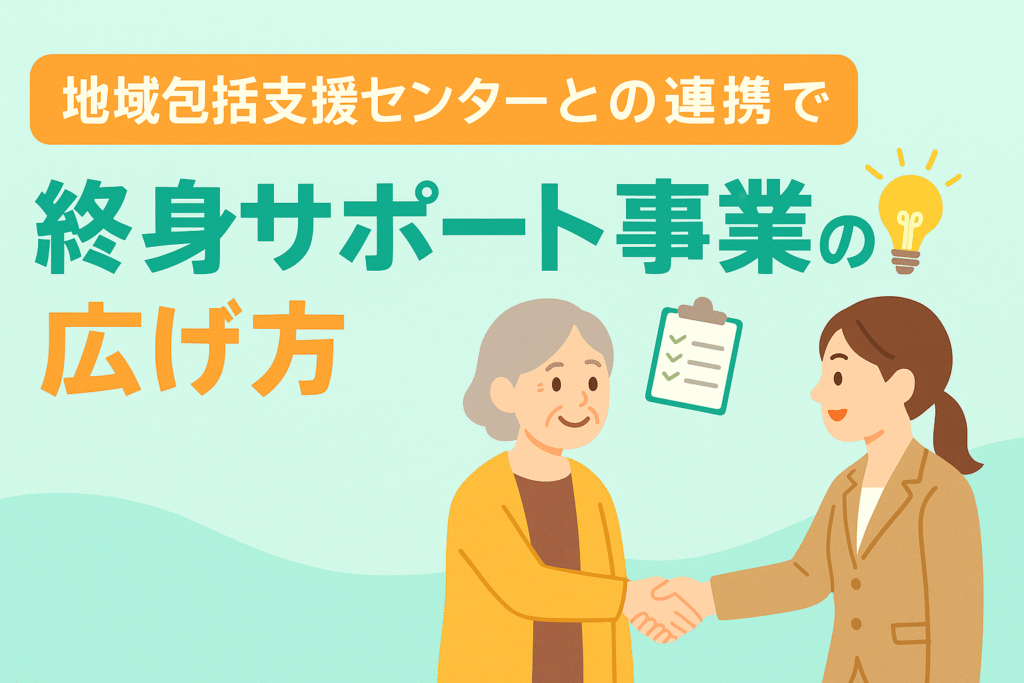
高齢化が進む今、「死後のことも含めて、生涯を通じて支援してほしい」というニーズが高まっています。そんな声に応える形で、近年注目されているのが、葬儀社による「終身サポート事業」です。
財産管理や死後事務、葬儀・納骨までをトータルで支援するこの取り組みは、一部の葬儀社で始まりつつありますが、本格的に広げていくには地域との連携がカギを握ります。なかでも重要なのが、自治体が設置する「地域包括支援センター」との連携です。
今回は、その連携方法や実現のポイントについて解説します。
目次
地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターは、市区町村が設置する高齢者の生活支援のための総合窓口です。
- 主な対象:65歳以上の高齢者
- 担当業務:介護予防、権利擁護、総合相談支援など
- 配置されている専門職:主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師 など
地域の高齢者やその家族を支える現場の最前線として、多くの支援ニーズを把握しているのがこのセンターです。
なぜ「終身サポート事業」と相性が良いのか?
終身サポート事業は、以下のような人生の終末期に関する包括的支援を行います。
- 生前整理
- 死後事務委任契約
- 遺言執行
- 永代供養 など
これらは、地域包括支援センターが把握・対応している支援ニーズと非常に親和性が高く、連携によって次のような効果が期待できます。
- 支援が必要な高齢者へ早期にアクセスできる
- 自治体機関との連携による安心感の提供
- 孤立を防ぐネットワークの構築
具体的な連携ステップ
地域包括支援センターとの連携は、以下のような流れで進めるとスムーズです。
センターへの訪問・ヒアリング
まずはセンターへ出向き、事業内容を説明します。現場の課題やニーズをヒアリングし、信頼関係を構築することがスタート地点です。
提案書の作成
独居高齢者や認知症リスクのある方など、対象者の属性に合わせたサポートメニューを明確にし、提案資料としてまとめます。
定期的な情報交換やケース会議への参加
センターと継続的な関係を築くため、定期的な意見交換や合同勉強会への参加が有効です。
委託事業やモデル事業としての展開
一定の実績ができれば、自治体との委託契約やモデル事業化の可能性も見えてきます。
実施時の注意点
● 専門家との連携が前提
介護や福祉の専門性が求められる領域では、社会福祉士や司法書士などとの連携が不可欠です。
● 法的リスクには要注意
金銭管理や死後事務は法的リスクも高いため、弁護士・行政書士などとの役割分担を明確にしておきましょう。
● 営業目的に見えない配慮を
終身サポートの趣旨が、単なる葬儀の営業と受け取られないよう、中立で誠実な姿勢を徹底することが信頼構築につながります。
まとめ|地域の課題を共に解決する存在へ
高齢単身者の増加、家族関係の希薄化など、現代社会には多くの課題があります。そうした中で、終身サポート事業は今後ますます必要とされるサービスになるでしょう。
地域包括支援センターとの連携は、そうした未来を見据えた第一歩です。
葬儀社が「地域の課題を共に解決するパートナー」として信頼を得ることで、持続可能な支援体制が実現します。